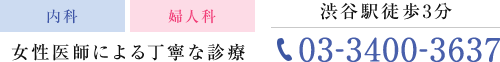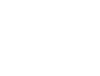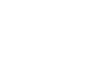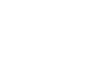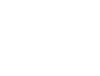うつ病
うつ病の症状
うつ病は気分の変調を基本症状とする病気ですが、不眠、食欲不振、肩こり・頭痛、性欲減退、生理不順など、さまざまな身体症状も引き起こします。次のような症状が1カ月以上続くようなら、うつ状態にあると考えてください。
- 元気が出ない
- いつも気分が暗い
- テレビがおもしろくない
- ずっと寝ていたい
- 人と会うと非常に疲れる
- 会話・会議がよく理解できない
- 物忘れがひどい
- すぐ涙を流してしまう
何といっても早期の発見、早期の治療が重要です。
うつ病の原因
これまで、うつ病は神経解剖学的に異常はないとされてきました。しかし、近年、記憶装置である海馬の委縮(脳細胞数の減少)が原因であるとわかってきています。うつ病は脳の病気、脳細胞の病気、脳神経ネットワークの病気です。
うつ病患者の場合、脳の左前頭前野機能が低下することで不快予測機能が優り、結果として悲観的思考が引き起こされます。
磁気刺激治療(rTMS)は、左前頭前野を活性化、あるいは右前頭前野を抑制することで左右のバランスを取り、うつ状態を改善していきます。
うつ病の改善策
うつ病の生涯有病率は6.2%、約16人に1人がうつ病を経験しています。うつ病はもはや特殊な病気ではありません。
近年、従来の三環系抗うつ薬に加え、SSRI、SNRI、NaSSAという新規作用機序を有する抗うつ薬が導入され、治療方法も進化中です。治療薬の選択肢も広がっており、副作用もどんどん軽減されています。当クリニックでは、保険内外診療、西洋薬療法、漢方薬療法に加え、最新の磁気刺激療法(rTMS)も行っております。
うつ病の事例
うつ病患者の30%は難治性となり、非常に治りにくく、そのため医療的な介入が不可欠です。ご自身の努力だけで解決しようとするのは危険です。
たとえば骨を折ったら自分だけで治そうとしますか? 普通はしませんね。うつ病は「こころの風邪」といったイメージの単純なものではありません。脳の病気であり、さらにいえば脳細胞の病気であり、だからこそ医療が必要なのです。早期発見、早期治療が大切です。
パニック障害
パニック障害の症状
予期し得ない、繰り返し起こるパニック発作からなる病像です。少なくとも1カ月間、再びパニック発作に襲われること、発作が引き起こすかもしれない事態(自動車事故、死、外傷など)に強い恐れを抱きます。
発作が駅のプラットホーム上、満員電車の中、雑踏の中、自動車の渋滞中などで起こるのではないかという不安と心配にかられます(予期不安)。次第に、発作が起こりうる状況を回避するようになり、日常生活、社会生活が著しく制限されることになります。
パニック障害の原因
一般人口の3.5%にみられ、女性は男性の2倍の発症率です。パニック障害は「心の問題」「弱さの表れ」「気の持ちよう」などでなく、脳内の不安や恐れに関する、神経系の機能異常に関連していることがわかっています。
不安と恐れで頭がいっぱいになり、前に発症した記憶を思い出してしまい、自ら発作を誘発します。そのためだんだんと行動範囲が狭まり、さらにネガティブな思考に陥るという悪循環が始まってしまいます。
パニック障害の改善策
治癒するのが容易ではありません。恐怖は、人間にとって根源的な感情であり、したがって厳格に制御されねばならないものです。この調整がうまく行われないために、パニック障害といった症状が発生すると考えられます。
発作の繰り返しを放置することは、この異常を強化することになります。一刻も早く医学的介入を行うべきです。
パニック障害の事例
突然激しい動悸を覚えたり、発汗、頻脈(ひんみゃく:脈拍が異常に多い状態)、ふるえ、息苦しさ、不快感、不安感、恐怖、めまいを感じてしまう症状を「パニック発作」といいます。このパニック発作が何度も繰り返されることで、生活がままならなくなった症状が、パニック障害です。
3分の1は病状が治まりおだやかになりますが(緩解)、45%は慢性化します。残りの4分の1は生涯にわたって緩解と再発を繰り返す経過をとります。
社会不安障害
社会不安障害の症状
日常生活のレベルを超えた不安や心配に、常に捕らわれた状態です。
日常のほとんどで、過度の不安と心配を感じ、それをコントロールすることができません。そのため強い苦悶を感じ、社会生活上うまく働くことができなくなります。多くの場合、胃腸の不調や倦怠感などの身体症状を訴え、自分の健康状態を常に心配しています。
社会不安障害の原因
社会不安障害は「心の問題」「弱さの表れ」「気持ちの持ちよう」などでなく、脳内の不安に関する神経系の機能異常に関連していることがわかっています。
自分の健康状態を常に心配していますから、何回も臨床検査を受けて、安心を得ようとします。したがって心療内科、精神科よりも、内科を受診することが多くなります。
社会不安障害の改善策
会話・会議がよく理解できない、プレゼンなどで過度な心配・恐怖を抱くといったことは日常生活でも往々にしてありますが、それが常態化しているのであれば問題です。
社会不安障害に限らず、まずはストレスを軽減・解消すること、寝ること、休むことが重要です。それでも不安や心配事、恐怖が解消されない場合は、一度受診をおすすめします。
社会不安障害の事例
誰もが日常で感じることのある不安ですが、その不安の強さが度を超えてしまい、さまざまな身体症状を伴って日常生活に支障をきたすのが、「社会不安障害」です。
まずは問診および測定によって、脳(こころ)の状態を数値化します。不安を定量化することで、客観的に診断・治療するのです。状態を明確にし、適切な治療を受ければ、病状が治まりおだやかになります。少しずつ治していくことが可能です。
摂食障害
拒食症の症状
正式名称を「神経性食欲不振症」「神経性無食欲症」などといい、無理な食事制限やダイエット、絶食を繰り返した結果、自分の意思とは関係なく身体が食べ物を受け付けなくなる病気です。
拒食症の原因
自分がどんな体型であるかなど、自分自身の外見における客観的なイメージを身体像(ボディーイメージ)と呼び、その身体像が正確に認識できなくなっていることを、ボディーイメージの障害といいます。拒食症は、このボディーイメージの障害と、肥満への強烈な恐怖が基礎となって形成されます。
拒食症の改善策
拒食症は、12歳から30歳の女性に多く見られます。過度の栄養失調から、衰弱状態にいたることも少なくありません。
拒食症患者の死亡率は10%近く、うつ病の合併は50%以上になります。投薬治療や丁寧な問診、心理療法を行いますが、症状が重い場合は、提携する専門施設をご紹介します。
拒食症の事例
拒食症患者は、自分の体型がやせているにも関わらず、それを正確に認識でないことが少なくありません。周囲から見れば、明らかに細すぎるものが本人にとってみればちょうどいいように、細いものすら太いように感じます。数値的に体重が軽いと認識していても、見た目において自分のことを太いと感じてしまうのです。
過食症の症状
短時間で異常なほど大量に食べます。空腹でなくとも食べる、満腹でも口に入れてしまう、といった過食衝動が続きます。過食前に感じる「食べたい!」という強い衝動のわりに、食べること自体への楽しみや快感はなく、過食後は「また食べてしまった」「また太ってしまう」といった強い罪悪感・自己嫌悪・自責感に襲われ、大変ひどく落ち込むことになります。
過食症の原因
明確な病因は不明ですが、ストレスの解消のため、あるいは拒食症の反動として起こることが多いようです。過食症患者は、無茶な食べ方をしている間、過食がやめられないという恐怖を抱きます。
過食症の改善策
放置すると重篤な状態になることもあるため、早めに診断・治療しましょう。過食嘔吐や下剤濫用による体質異常、食道の炎症とそれによる吐血、脱水、月経不順や無月経などあらゆる症状を診察・対応します。
投薬治療や丁寧な問診、心理療法を行いますが、症状が重い場合は、提携する専門施設をご紹介します。
過食症の事例
太ることに異常なほど強い恐怖を感じるため、無理やり嘔吐したり、下剤を大量に飲もうとしたりする患者さまもいます。
自己誘発嘔吐を繰り返すと、やがて容易に吐けるようになり、下剤についても規定の使用量をはるかに超えた量を使ってしまいます。嘔吐や下剤乱用のほか、過食後に絶食したりするなど、反動による代償行為を繰り返します。
出産後のママへ:産後うつ病への理解と対応
渋谷からだと心のクリニック(旧:つのおクリニック)では、産後うつ病に対し、心理カウンセリング、薬物療法、非侵襲的な磁気刺激治療を組み合わせた治療を提供。産後のホルモン変動やストレスによる症状に、専門医が全面的にサポートし、早期発見・治療を重視しています。
ストレス
ストレスの症状
うつの場合、患者さまが置かれた環境に自我が適正に機能できず、内的・外的世界に対して破綻をきたしたといえます。この状態が長く続くと、心身症・うつ病・神経症・パニックなどの明らかな病的症状を呈します。
ストレスの原因
ある出来事が身にふりかかってきたとき、その人の自我の状態(知覚・思考・行動の総体)によってストレスとなったりならなかったりします。同じストレスでも、ある人にとってはうつの原因になり、ある人にとっては成長のバネになります。
ストレスの改善策
境界を越えて病気になってからの回復は、決して順調にいくものではありません。時間もかかります。当クリニックでは、ストレスがまだ未病の段階にあるうちに対応し、調和的世界に戻る手段を患者さまとともに考える外来を設けております。
心理テスト、交流分析など、そして何よりもまずお話を丁寧に聞くことを通し、一緒に考えてまいります。
ストレスの事例
過度なストレスを受けると、身体はホルモンバランス(特に副腎皮質ホルモン)の乱れ、自律神経系の乱れをきたします。そして発汗、筋肉の緊張のほか、頭痛、動悸、吐き気などのあらゆる「身体的症状」、絶望感、無力感、自殺衝動といった「精神的症状」、アルコール依存、薬物依存などの「行動的症状」を引き起こします。
心身相関現象
心身相関現象の症状
「病は気から」とよくいわれるように、心のありようと体の状態は密接に関係しています。一方の変調はかならず他方に影響し、悪循環を形成していきます。体の変化は不可逆的なところまで進み、それがさらに心の状態を悪化させていきます。
心身相関現象の原因
大勢の人の前に立って歌う、あるいは発言するようなとき、あがって脈拍が早くなったり、手のひらや脇の下に汗をかいたり、口が乾いたりします。これらは、「うまくできるだろうか」という心の不安が体に影響を及ぼしている例で、これを心身相関現象と呼びます。
心身相関現象の改善策を教えてください
心身相関現象の悪循環から脱するには、心の問題には心身医学からの対応、身体の問題には内科的治療が必要です。心身の両面から対応できるのが当クリニックです。代表的疾患は以下のようなものがあります。
心身相関現象の事例
| 血管 | 胃腸 | 体質 |
|---|---|---|
| 高血圧 | 胃十二指腸潰瘍 | 肥満 |
| 狭心症・心筋梗塞 | 過敏性腸症候群 (下痢・便秘・膨満) |
摂食障害 |
| 心臓神経症(動悸) | 心因性嘔吐 | 糖尿病 |
| 慢性胃炎 | ||
| 潰瘍性大腸炎 |
| 呼吸器 | 皮膚 | 神経 |
|---|---|---|
| 気管支喘息 | アトピー性皮膚炎 | 頭痛 |
| 過換気症候群 | 蕁麻疹・湿疹 | 斜頚・書痙 |
| 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) |
全身掻痒症 | 自律神経失調症 |
| 円形脱毛症 | 慢性疼痛 | |
| 神経性頻尿 |
| 女性特有 | 関節 |
|---|---|
| 月経困難症 | 慢性関節リウマチ |
| 月経不順 | |
| 更年期障害 |